週刊東洋経済の特集「学校が危ない 教育劣化は日本経済の大問題だ」という特集があった。日本の教育の将来をうれいたすばらしい企画だ・・・と期待したわたしがバカでした。管理職と日教組と現場教員からのひとりよがりの意見ばかりで、まったくフェアに実態を反映していないと思えるからだ。この企画への違和感は、また別の機会にのべたいとおもう。
「最強・秋田モデル」は、「秋田モデル」か
その中で、「最強・秋田モデル」と紹介している。紹介されている授業はべつに秋田独自のモデルではなく、どこの都道府県でも業界的に”よい授業”とされているスタイルだ。論理的にかんがえると、ここから秋田の全国学力テストの結果がよい、ということはみちびけないとおもう。
もし文章の中からよみとれるとしたら、沖縄県が「秋田県から戻ってきた先生の授業を参考に改善を徹底し、県独自のテストも増やし、最下位を脱出した。」というくだりではないだろうか。「独自のテストを増やし」がポイントだとおもう。ようは学力状況調査の対策をしたのだろう。これ自体は、わたしは勉強スタイルの王道だとおもう。普遍的な学力などない。必要な選抜試験におうじた対策をとればいい。ただ、それを秋田モデルの成果だ、と相関関係だけをみて、因果関係をかえりみない議論があぶないといっているのだ。
そして、秋田県の中学までの成績は優秀だが、大学のセンター試験の平均点は、全国平均以下だ。ここにもう、答えがでているじゃありませんか。
生徒指導の困難さは、授業のつまらなさがボトルネックか
また、秋田モデルに詳しい秋田大学教育文化学部の教授の話によると、「まず授業をしっかりやるすること。面白ければ児童はついてくる。それが結果的に生徒指導になる。授業を後回しにしてはダメだ。」という。これもわたしの感覚だと因果関係をさかさまにとらえていて、ほんとうにつまらない授業をすれば学級崩壊しますよ、そりゃ。けれども生徒指導(生活指導)を徹底できない教員は、いくら教材研究をしてもダメな教師なのである。この倒錯した認識が学級崩壊を助長している。まずは児童生徒にナメられない(べつに頭ごなしにおさえつけるわけではないし、これは企業で管理職が部下にたいする姿勢でもおなじだろう。ようはこの人のいうことはきかなくては、と児童・生徒にかんじさせることがだいじなのである)、その上で信頼関係をきずく。その上でおもしろい、わかりやすい授業をやる。
「答えをすぐに言わないとことん考える探求型」はすべての児童にとって福音か
算数で教科書をひらかせるのがきらいな教師は多い。教科書は”とてもわかりやすい”ので、教科書をみてしまうと授業が成立しなくなるのではとおそれているようだ。教科書をひらかせないで、教科書の文章を黒板にかき、それをうつさせ、式をかかせる。そしてその解法を自力解決していくのが、秋田にかぎらず今の小学校の定番スタイルだ。200-127という問題が取り上げられているが、200を100ずつにわけて、100-100と100-27にすれば簡単ですという児童、筆算でとく児童、文章であらわす児童といった具合に”多様なかんがえ”がでてくる。自力解決をするととうぜん児童の”自力”の差が如実にでるし、”みんなの発表したかんがえ”は多様すぎて教師が整理しないことにはなにをやっているのかすらわからない児童もすくなからずでてくる。(それでもわからない児童もでてくる。)そして最後にのこるのは、教科書と同じようなノートができているだけで、練習問題をやる時間は圧倒的になくなる。そのため練習問題は家庭学習になり、家庭の教育に対する姿勢がそのまま(少なくともペーパーテストの)学力にあらわれてくるのだ。それですべての児童が最低限の理解にいたれるのだろうか?
とにかく秋田モデルと全国学力テストでの優秀さの相関は、もういちどよくかんがえてから称揚したほうがいいとおもうのだが。
中沢 良平(公立小学校教師)
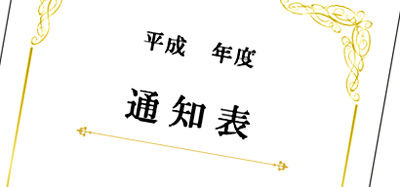




 新たな価値の創造は根づくか
新たな価値の創造は根づくか